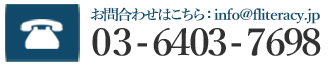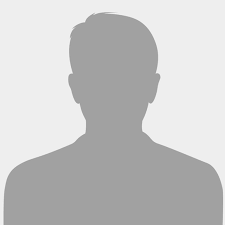最終更新日:2020年6月16日 家計管理ライフプランニング
金融リテラシー『家計管理とライフプランニング』
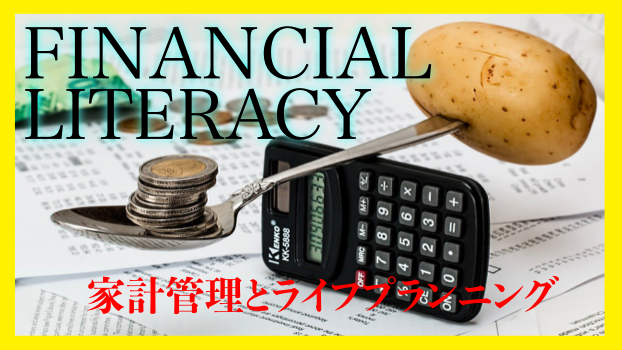
金融リテラシー『家計管理とライフプランニング』
個々の金融リテラシーを向上させましょう!
本日は、金融経済教育推進会議コアコンテンツ内で説明されている『家計管理とライフプランニング 』について取り上げてみたいと思います。
- ~働いて「稼ぐ」ことと、将来に備えることについて~
1-1.稼ぐということは
- 労働と収入
1-2.付加価値
(1)働いて「どの程度の収入が得られるか」は、みなさんが提供できる「付加価値」の大きさと関係しています。
(2)多くの人が働いて「付加価値」を世の中に提供しています。
(3)働き方によって、収入は異なります。
(4)社会や経済の変化に応じた、柔軟な働き方も大切です。
注「付加価値」(value added)とは、「新たに付け加えられた価値」のことで、たとえば人や企業が、より良い商品やサービスを世の中に提供する(そのプロセスの一部を担う)ことを指します。一人一人が付加価値を生み出すことで経済は成長し、社会の発展にも貢献します。
1-3.多様な働き方(稼ぎ方)
(1)雇用される
- 会社員(正社員、派遣社員)
- 公務員
- アルバイト、フリーターなど
(2)それ以外
- 家業などを継ぐ
- 起業する(会社を起こす)
- フリーランスなど
1-4.収入と支出
(1)生涯の収入、支出のイメージをつかみましょう。
収入と支出をバランスさせることが大事です。
日常生活でも、家計の収支を管理し、黒字を確保する(お金を貯める)習慣をつけましょう。
(2)「将来やりたい夢」や「人生の3大費用」にどうお金を準備するか、考えましょう。
1-5.一生涯の収入と支出(勤労者家計の平均的な姿)
生涯収入:約2.7億円
生涯支出:約2.4億円
※65歳で収入を支出が上回ってしまうのか!
総務省「家計調査」(2016年)
収入は可処分所得、支出は消費支出+土地家屋借金返済のデータから試算
1-6.雇用形態による平均年収の違い
正社員527万円
正社員以外297万円
推定年収=「きまって支給する現金給与額」×12ヶ月+「年間賞与その他特別給与額」として試算
厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査」
平成28年賃金構造基本統計調査
1-7.収入と支出の分布
年間収入額 中央値:327万円,平均値:417万円
年間支出額の分布図 中央値:267万円,平均値:284万円
1-7.収入と支出の分布
収入は可処分所得、支出は家計支出、各中央値および平均値以下の世帯割合は均等分布を仮定して試算
1-8.人生の3大費用とは
子育て・教育 :(幼~高=公立、大=国立)約800万円、(幼~大=私立)約2,200万円
住宅:建売住宅 約3,300万円、マンション約4,300万円
老後:(平均)約8,000万円
、(ゆとりあり)約1億500万円
出所:内閣府、総務省、文部科学省、国民健康保険中央会、全国大学生活協同組合連合会、住宅金融支援機構、生命保険文化センターの資料により試算。
1-9.65歳から先の収支バランス(夫婦モデル)
支出8,000万~1億500万円
平均コース約8,000万円 月27万円
ゆとりあるコース約1億500万円 月35万円
定年後25年間の年金収入6,600万~ 9,300万円
一人は正社員、一人はパート
または専業主夫・婦で約6,600万円(月22万円)
二人とも正社員で約9,300万円(月31万円)
平均コース=総務省「家計調査」(2016年)
高齢夫婦無職世帯の実支出
ゆとりあるコース=生命保険文化センター「生活保障に関する調査」(平成28年度)、
老後2人で暮らしていくうえでの最低必要額(22.0万円)+経済的にゆとりのある老後生活を送るために必要な追加金額(12.8万円)
年金=厚生労働省報道発表(2018年1月26日)、平成30年度の新規裁定者の年金額の例(厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金))から試算
支出 > 収入となりそうなら、65歳までに資産形成が必要。
支出 > 収入となりそうなら、65歳までに資産形成が必要。
その方法は?
金融リテラシーを向上させ、実体経済と金融経済の両立を実現する必要があります。
本協会で、正しい金融知識、正しい投資方法や手法を習得していただければと思います。